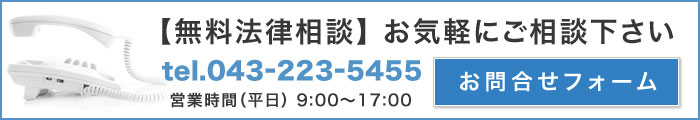被害者のための交通事故慰謝料の解説
慰謝料とは
 慰謝料とは、厳密には様々な考え方があるものの、一般的に、肉体的・精神的な「苦痛」に対する賠償と考えられています。
慰謝料とは、厳密には様々な考え方があるものの、一般的に、肉体的・精神的な「苦痛」に対する賠償と考えられています。
慰謝料は,交通事故の賠償の金額の中で大きなウエートを占めるものの1つで、交渉が必要になりやすいところですので、きちんと相場を知っておく必要があります。
(慰謝料が請求できるケースについてはこちら→「交通事故で慰謝料を請求できるケース」)
この慰謝料の金額を算定するにあたって考慮されうる事情としては,怪我の内容や治療期間の長さに加え,財産的に換算することが難しい私生活上の不利益,相手方の態度等,多岐にわたります。
実際に支払いを受けるには,この「苦痛」をお金に換算することになりますが,苦痛を数値化することはそれ自体難しい問題であることに加え,人それぞれ苦痛を感じるポイントや置かれた状況も異なりますので,この作業は非常に困難を伴います。これを、個別の事案の様々な事情をくみ取って事案ごとに金額を決めようとすると、判断する人(裁判官)の考え方にも大きく左右されることになり、不公平が生じる可能性が高くなります。
そのため、実務上は慰謝料の額の定額化が進んでおり、そこまで細かい事情に踏み込まずに金額が算定されています。
※死亡慰謝料については、比較的個別の事情がくみ取られて算定される傾向にあり、事案によって金額にかなりの幅が生じています。これは、失われたものがあまりに大きく、被害者遺族の精神面でのダメージを特に考慮する必要があるからだと考えられます。
慰謝料の種類
交通事故で問題となる慰謝料の種類には以下のものがあります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我を治すために入院や通院をしていた期間に発生する慰謝料です。
この入通院の期間に痛みなどによって辛かった、通院が大変だった、生活に支障が出た、やりたいことができなかった…といった苦痛に対して支払われるものです。
怪我の重さによって金額が変わることになりますが、一般的には、入院日数がどれくらいだったか、怪我が治るまでの通院期間の長さはどれくらいだったのかによって金額が決まってきます。
自賠責保険の算定基準のように、「実際に通院した日数(通院頻度)」が直接金額に影響を与えるわけではありません。
したがって、通院すればするほど慰謝料の額が大きくなるわけではありません。治療はあくまでも身体を治すために行うものであることを忘れないようにしましょう。慰謝料目的に通院回数を増やそうとすることは不正請求とみなされてもおかしくありません。
※入通院慰謝料と通院日数の関係についてはこちら→「交通事故の慰謝料と通院日数」
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、入通院を続けても症状が完全になくならずに後遺症として残ってしまった場合に、入通院を終えた日(正確には症状が固定した日)以降の精神的苦痛に対して支払われるものです。
後遺障害慰謝料は、裁判上、自賠責保険で認定される後遺障害等級にしたがって定額が支払われることが一般的です。醜状障害のように、逸失利益としては評価しづらい後遺症については、慰謝料を増額することで調整が図られることもあります。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別枠で支払われるもので、症状固定前の苦痛に対しては入通院慰謝料、症状固定後の苦痛に対しては後遺障害慰謝料で賠償金を支払ってもらうというイメージになります。
「症状固定」とは、これ以上治療をしてもよくならないという状態に至った時点のことを指し、この前後で賠償金の支払い方法が変わるということです。
※後遺障害の慰謝料についてはこちら→「後遺症の等級と慰謝料について」
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、死亡した被害者が家庭でどのような立場にあったのかによって金額が変わってくる傾向にあります。これは、残された遺族が被る不利益の度合いを考慮した結果です。
そのため、一家の大黒柱が亡くなったような場合には、遺族の生活に与える影響が大きく慰謝料の額も高額になり、独身者が亡くなった場合には慰謝料の額が低くなる傾向にあります。
その他、年齢なども考慮要素となります。
※死亡事故の慰謝料についてはこちら→「死亡事故の慰謝料」
物損に関する慰謝料
物損に関する慰謝料は、裁判上は否定されることが基本です。例外的に認められるケースとしては、家屋が破損したとか墓石が破損したといったものがあります。車が壊れたり買い替えることになって苦痛だという程度では認められないと考えておいた方が良いです。
慰謝料算定の基準
慰謝料算定の基準として代表なものは,日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する「赤い本」と呼ばれる本に記載されている基準です(「弁護士基準」などと呼ばれることもあります。)。
弁護士が交渉するときに用いるのも,主にこの基準です。
通院1か月でいくら、入院1か月でいくら、といった具合に金額が定められていて、受傷からの時間の経過と共に単価は下がっていきます。これは、受傷当初が最も症状や精神的負担が重く、時間の経過と共に改善していくことを反映しています。
実際に法律的に認められる慰謝料の額とは
上で説明した基準は,あくまでも目安に過ぎず,各被害者の実情を正確に把握しているとは限りません。
そのため,法律的に認められる慰謝料の額を正確に知ろうとする場合,最終的には,裁判所に判断をしてもらわなければなりません。
そして,裁判所は慰謝料の金額を裁量によって自由に決めることができるとされています。
したがって,上記の基準はあくまでも目安であり,実際には,同じ治療期間であっても,個別の事情によって,増額したり減額したりすることが当然あり得るのです。
特に、入通院慰謝料は、弁護士基準によれば入院と通院の長さによって金額が決まってくることになりますが、実際に裁判で審理されると、「入院が延びたのは実は被害者の家族の都合によるものだった」とか、「怪我自体は大したことがないのに、異常に長い期間通院していた」といったことが明らかになることがあります。
こういった場合、計算の元となった入通院の長さに修正が入る可能性がありますので、想定していた金額とギャップが生じることがあります。
したがって,弁護士基準が算定された金額が,必ずしも自分の慰謝料の金額になるわけではないということに注意する必要があります。
特に、最近ではインターネットの情報を鵜呑みにして慰謝料目的に過剰な通院をしている人がいますが、そうした人は要注意です。
保険会社の対応
保険会社の対応も以上のような裁判の現状を踏まえたものになります。
金額が法律的に見て,きっちりと決まっているものであれば,保険会社もその金額の支払いを拒むことはないでしょう。
しかし,慰謝料は,実際には様々な事情が考慮されて算定されるもので,必ずしも一定ではありません。
実際に、裁判になると保険会社が付けた弁護士から、高い確率で「通院が長過ぎる(必要のない通院をしている)」といった主張が出されることがあり、裁判所もその主張を認めることもあるのです。
保険会社としては、目安となる金額よりも支払いが少なくても済む可能性がある以上、敢えて相場どおりの金額を支払う理由がありません。
したがって,「保険会社が提案してくる金額は,弁護士基準よりも低い」と考えてよいです。
例外的に裁判基準もしくはそれを上回る支払いに応じることがあるとすれば、被害者にも若干の過失がある等の理由で、自賠責保険で計算した慰謝料の方が裁判基準よりも高くなる場合や、休業損害や過失割合など他の項目で争いがある場合、その部分を譲歩する代わりに慰謝料を満額にするといったことが考えられます。
弁護士による交渉
 このように,保険会社が基準よりも低い金額を提示してくることはある意味当然とも言えるのですが,問題は低すぎるのではないかということです。
このように,保険会社が基準よりも低い金額を提示してくることはある意味当然とも言えるのですが,問題は低すぎるのではないかということです。
慰謝料にはあいまいなところがあるため,被害者にとってとことん不利な解釈をしていけば,果てしなく金額は下がっていきます。また,通常,被害者はそれがどれほど不当なのかを知るすべがありません。
そのため,保険会社からは、裁判所が一般的に認める相場よりも著しく低い金額が示されることが少なくありません。
そこで,弁護士が金額の妥当性について交渉を行う必要が出てくるのです。
既に述べたように,弁護士が用いている基準はあくまでも目安に過ぎませんが,実際にはかなり重視されており,裁判所もこの基準で算出された額をそのまま認めることも少なくありません。そのため、交渉でもこの基準は有効に使えます。
一般の方でも、この基準を使うことで保険会社と交渉をすることは不可能ではありませんが、弁護士との違いは、相手があくまでも支払わないと言ってくる場合に裁判を起こすことができるかどうかです。
裁判手続を行うためには専門的な知識が必要となり、既に述べたように、裁判になれば保険会社側の弁護士はそれまで争っていなかったような点まで徹底的に争ってきますので、これらに対して一般の方が適切に対応することはまず不可能といってよいです。
そのため、一般の方が交渉する場合、裁判まではできないということが前提となるため、保険会社としては「支払えない」の一点張りに終始していればよくなります。
これに対し、弁護士が交渉をする場合、相手が不当な主張を繰り返すようであれば、交渉を打ち切って裁判を起こすことが可能です。
保険会社としても,裁判で時間と費用をかけた上に基準に近い金額を支払うことはムダであるため,実際には,裁判に至る前に相当な金額が支払われることが多いのです。
これが、慰謝料に関する保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合のメリットです。