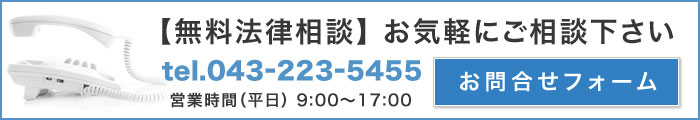3つの慰謝料基準と慰謝料相場
目次
3つの慰謝料基準?
このホームページをご覧になっている方の中には,交通事故の損害賠償請求についてインターネットを使って色々と情報を集められている方もいらっしゃると思います。
そうした中で、慰謝料の計算について3つの基準があるというものを目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
多くのホームページで言われているのは、「慰謝料の計算について,裁判基準(又は弁護士基準),任意保険基準,自賠責基準と3つの基準がある」というもので、「裁判基準>任意保険基準>自賠責基準」の順で金額に違いがあるというものです。
そのため,弁護士が裁判基準で交渉をすることにより,慰謝料の額が増額する…といった具合です。
しかし,これだけでは分かりにくいですし,必ずしも正確ではありませんので、もう少し詳しくご説明いたします。
慰謝料の基準が必要な理由
慰謝料とは,基本的に精神的苦痛に対する賠償のことを指しています。
しかし,自分に生じた精神的苦痛が金銭的に見たときにいくらになるのかを判断するのは非常に難しいです。それに,これが何となく決められるということになれば,人によって高くなったり低くなったりして不公平が生じてしまいます。
そのため、慰謝料の額を決めるための基準が必要になるのです。以下では、各基準の概要と比較について解説します。
A 自賠責基準
自賠責保険は,強制加入の保険で,保険金の支払いは明確に基準が定められています。
①傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料とは、入通院をしていた治療中の時期の慰謝料のことを指し、 1日当たりの慰謝料を4300円(※)とした上で,実際に通院した日数を2倍したものと通院をした期間を比較した小さい方の数字をかけるというのが基本的な考え方です。
例えば、4月1日~4月30日までの30日間通院していれば、基本的に4,300円×30日=129,000円となり、これが慰謝料の上限額となりますが、この30日間のうちで実際に通ったのが5日間に過ぎなければ、慰謝料の額は4,300円×5日×2=43,000円となります。
また,計算方法の基準があるほかに,保険金の上限額が決められているため,自賠責保険金の額を考えるときは,この点も重要となります。
傷害による損害(治療中の損害)に対して支払われる保険金額の上限は,120万円とされています。
そのため,仮に1日当たり4300円で慰謝料を計算したとしても,治療費や休業損害等と合算して120万円を超える部分があれば,その分は支払われないのです。
例えば、通院回数が多く、治療費だけで120万円を超えていたような場合、自賠責保険で支払い可能な慰謝料は0円となります。
詳しくはこちら→「慰謝料と通院日数の関係」
※令和2年4月1日以降に発生した事故については1日当たり4200円→4300円になっています。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状が消えないまま固定し、その症状に後遺障害等級が認定された場合に支払わわれる慰謝料のことをいいます。
自賠責保険では、認定された後遺障害等級に応じて、例えば14級であれば32万円といった具合に金額が定められています。
こちらにも上限額が定められていて,14級の場合は75万円です(後遺障害による賠償の中には,慰謝料のほかに逸失利益というものが含まれていますので,合わせて上限が75万円となります。)。
※いずれも,複数台が絡む事故の場合には,上限額が増えることがあります。
B 任意保険基準
任意保険とは、自賠責保険では足りない部分を補てんするための上乗せ保険であり、加入が強制されているものではありません。しかし、交通事故の賠償が時として非常に高額となり、これを個人が支払おうとすれば生活が破綻してしまうということにもなりかねないため、多くの人が加入しています。
各保険会社は、交通事故の賠償金に関する基準(任意保険基準)を独自に定めていますが、現在は公表はされていません(人身傷害保険の基準が参考になります)。
任意保険が上乗せ保険である以上、自賠責保険の基準よりも高くなるのは当然のように思えます。
しかし、実際に被害者が提示されている金額を見ると、「弊社基準<自賠責基準」として、自賠責基準での支払いにとどめようとすることが思った以上に多いです(後述)。
C 裁判基準(弁護士基準)
裁判基準(弁護士基準)とは,過去の裁判のデータを元に作成された基準で,裁判をすればおそらく裁判所がこれくらいの金額で認定をしてくれるだろうという目安の金額を示しています。
特に有名なものとして,日弁連交通事故相談センター東京支部が作成した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(「赤い本」)というものがあります。
※「赤い本」について詳しくはこちら→『「赤い本」について』
もっとも,この基準で計算をすれば相手方がすんなりと支払ってくれるかというと、そうではありません。
なぜなら,これもあくまで目安に過ぎず,実際に裁判をしたとしても完全に金額が一致するわけではないため,相手方が納得できないとして支払いを拒めばそれまでだからです。
しかし,裁判を行えば,裁判基準に近い額が認められる可能性が高いのは事実であり,相手方としても,時間と労力をかけて裁判で争った結果,裁判基準の金額を支払うのは避けたいところです。
そこで,弁護士が交渉を行うことで,裁判を行わなくても、裁判基準に近い金額での示談が可能となります。
その結果,弁護士へ依頼した場合としなかった場合とで,受け取れる金額に差が出ることが非常に多いのです。
①傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料の計算は、入院と通院にどの程度の日数がかかったかによって基本的に決まってきます。
そうすると、入院と通院に日数かければかけるほど慰謝料の額が大きくなりそうですが、もちろんそんなことはなく、本来は早く終えるべきであったところを被害者の事情で引き延ばしたり、医師が治る見込みもないのに漫然と治療を続けていたような場合には、その期間は慰謝料の算定からは除外されることになります。
したがって、より正確には、「事故で負った怪我を治すのにどの程度の時間が必要だったか」ということによって金額が決まると考えた方がよいでしょう。慰謝料の金額を釣り上げる目的で通院回数を増やすことが許されなことは言うまでもありません。
自賠責基準と異なるのは、通院の開始から終了までの間に実際に何回通院したかは基本的に問題とならないということと、1日当たりの慰謝料の額は、事故当初が最も高く、その後徐々に減額されていくという点が挙げられます。
慰謝料の単価が徐々に減っていくことになるため、自賠責基準のように、慰謝料の「日額がいくら」といった金額はありません。
また、事故で負った怪我の内容が打撲・捻挫に過ぎないのか、骨折などの器質的変性を伴うのかによって、基準が2通り存在していて、後者の方が慰謝料の額は高くなります。
さらに、特に酷い怪我を負った場合には加算があるとされていて、より実態が反映されるようになっています(実際の裁判では、裁判官が個々の事情に応じてさらに細かい調整をすることがあり得ます)。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、自賠責基準と同様、認定された後遺障害の等級によって決まるのが基本です。
裁判では、醜状障害や嗅覚・味覚障害、生殖機能に関する障害のように、後遺障害逸失利益として評価するのが難しいような後遺症の損害について、慰謝料を増額することで調整するということも行われます。
自賠責基準と任意保険基準の比較
保険金の上限額による違い
自賠責基準はあくまでも「120万円の上限を超えない範囲で」という条件付きのものであるのに対し、任意保険基準では保険金額は無制限とされていることが多く、上限額の設定がある場合でも、自賠責保険ほど低額ではありません。
そのため、特に治療費が高額になるなどして自賠責保険金の上限額を超えている場合、慰謝料は任意保険基準で計算した方が高くなることが多いですが、自賠責保険の基準と同額の提示をされることもあります。
自賠責保険の上限額120万円を超えない場合、任意保険基準の計算の方が低くなることも多く、その場合、任意保険会社は、賠償金額を自賠責基準にあわせるということを行います(結果として自賠責基準の額と同額になります)。※二重取りはできません。
計算の具体例
例えば、自賠責基準で治療費50万円、慰謝料60万円の合計110万円というケースを見てみます。
この場合、任意保険基準だと、治療費50万円は変わらなくても、慰謝料の額は40万円にしかならないということがあります。この場合、任意保険基準の合計額は90万円にしかなりませんが、実際の支払額は、自賠責保険の額と同じ110万円となります。
次に、自賠責基準で治療費70万円、慰謝料60万円の合計130万円というケースを見てみます。
この場合、実際に自賠責保険から支払われるのは120万円までですので、残りの10万円は支払われません。
これに対し、任意保険では120万円の制限はありませんが、計算の結果慰謝料が40万円だとすると、治療費と合算して110万円にしからならず、自賠責保険の方が高くなります。この場合、やはり自賠責保険の金額に合わせる形になり、120万円が支払われます。
最後に、治療費が120万円を超えているケースを見てみます。
この場合、自賠責保険からは慰謝料は1円も払われませんので、任意保険基準で任意保険会社から慰謝料が支払われることになります。このケースでは、任意保険基準>自賠責準という関係になっています。
自賠責基準<任意保険基準とは限らない
以上のように、任意保険は自賠責保険では補償が不足する部分を補うための保険のはずなのですが、実際には計算上は自賠責保険の額を下回っていたりして自賠責保険金以上の補償を行わないということも少なくありません。
上記の例でも触れましたが、例えば、「自賠責基準で計算した場合の慰謝料の額が60万円で、任意保険基準で計算した場合の慰謝料の額が40万円となる」といったことがしばしば見られます。このような場合、任意保険会社は、自賠責保険基準を下回らないように、支払額を自賠責保険に合わせて60万円とすることになります。
なぜこのようなことが生じるかというと、「人身傷害保険」(対人賠償責任保険とは違います)の約款を見ていただくと分かるのですが、保険会社が設定している慰謝料の計算方法は、自賠責保険基準をベースにしつつ、事故当初は自賠責基準の100%、90日経過後180日までは自賠責基準の75%、180日経過後270日までは自賠責基準の45%…といった具合に徐々に自賠責基準と比較して慰謝料の額が低下していくのが一般的だからです。
このように慰謝料の額が時間の経過と共に小さくなっていくのは、先に見た裁判基準の考え方も共通するものです。
厳密にいうと、任意保険基準は人身傷害保険基準と一致しているとは限らず、保険会社が初めから自賠責準を上回る提示をしてくることもあるのですが、実際に保険会社から示された計算書を見ると、この人身傷害保険基準の計算にのっとって計算しているものをよく見かけます。
したがって、多くのホームページで書かれているように、任意保険基準>自賠責基準という関係は必ずしも成立していませんし、逆になっている場合も決して少ないものではありません。むしろ、傷害部分(治療期間中の部分)については、自賠責基準の方が任意保険基準よりも高いのが基本であると考えた方が実態に即しています。
そのため、私は、インターネットで任意保険基準>自賠責基準などと書かれているのを見ると、本当に交通事故を専門的に取り扱っているのか疑問に感じます。
いずれにせよ,対人賠償保険は,あくまでも加害者から被害者への賠償に関する保険であり,加害者がどこまで責任を負わなければならないかは法律で決まるものですので、被害者が任意保険の基準に従わなければならない理由はありません。
不当な金額が提示された場合,毅然とした態度で交渉を行うことが必要となります。
裁判基準の方が低くなるケース
これに対し、裁判基準が自賠責準や任意保険基準を下回ることはほぼありません。
しかし、ここでも例外はあります。
裁判基準の方が低くなるケースを考えるにあたっては、①慰謝料の計算方法の違いと②過失相殺の処理の違いを考える必要があります。
慰謝料の計算方法の関係
まず、慰謝料の計算方法ですが、自賠責基準では、上で見たように通院1日当たりの単価が決められいて、通院が長くなるほど(あるいは通院実日数が多くなるほど)慰謝料の額が高くなっていきます。
通院の頻度が2日に1回以上であれば、通院期間が90日で38万7000円、180日で77万4000円、300日で129万円となります。
これに対して、裁判基準も通院の長さによって金額が変わるという点は基本的に変わりませんが、最も用いられている「赤い本」という書籍で示されている打撲・捻挫等の慰謝料の基準は、3か月で53万円、6か月で89万円、10か月で113万円となっています。
これらを比較していただくと分かるとおり、半年時点では裁判基準の方が高くなっていますが、10か月の時点では逆転して自賠責基準の方が高くなっています。
このような違いが出る理由は、自賠責基準では通院がどれだけ長くなっても単価が一律なのに対し、裁判基準では、期間が長くなるにつれて単価が下がっていくためです。これは、事故当初と比べると症状が緩和していくことが関係していると思われます。
こうした自賠責保険基準での慰謝料の計算方法がインターネットで紹介されている影響で、「通院をすればするほど慰謝料が増える」と安易に考える人がいます。
しかし、上記の例のように300日通院すれば自賠責保険で慰謝料が129万円が受け取れるかというとそうではありません。
既に述べたように、自賠責保険には限度額があり、後遺症分を除けばその額は120万円です。しかも、この120万円の中に、治療費の他に休業損害や通院交通費なども含まれることになります。したがって、そもそも満額でも120万円であることに加え、それまでにかかった治療費等を除くことになるので、実際に受け取ることのできる額は大きく目減りします(治療費だけで120万円を超えていれば、慰謝料に振り分けられる額はありません)。
慰謝料の額を釣り上げることを目的としてせっせと整骨院でマッサージを受けたような人の場合、治療を終える頃には施術費用が大幅に膨らみ、本来受け取れるはずだった慰謝料も受け取れないということがあり得ます。また、過剰診療が発覚すれば、その分の賠償を受けることもできません。
しかし、この限度額には例外があり、複数台が絡む事故で、加害者が2名いるような場合に、自賠責保険が2つ使えるということがあります。この場合、上限額が2倍の240万円になりますので、治療費などの額にもよりますが、上記の例で慰謝料として129万円を受け取れる可能性があります。そうすると、裁判基準よりも自賠責基準の方が慰謝料の額が大きいということになります。
過失相殺の関係
次に、過失相殺の関係があります。
被害者にも事故の発生に何らかの落ち度がある場合、裁判基準では過失相殺といって、加害者はその限度で支払いの責任を免れ、損害額の一部が被害者の負担となります。
この被害者の負担部分は、慰謝料だけではなく、治療費など全てにかかってきます。
例えば、治療費50万円、慰謝料の裁判基準100万円、過失相殺50%で治療費は全額支払済みというケースでは、50万円+100万円の計150万円の50%である75万円が相手の負担となり、このうち50万円は治療は既に相手方から支払われていますので、最終的に受け取れる慰謝料の額は25万円ということになります。
これに対して、自賠責基準では、傷害部分(死亡事故や後遺症部分ではない通院中の部分)では過失が7割未満なら過失相殺されないということになっていますので、過失相殺50%であれば、特に減額はありません。
そこで、この間に一定程度通院をしていれば、限度額120万円から治療費50万円を引いた70万円が慰謝料として受け取ることのできる上限額となります。
このケースで自賠責基準の上限額で慰謝料を受け取った場合、金額は裁判基準の3倍弱となります。
治療の打ち切りが絡むケース
怪我の治療のための通院が一定期間を超えてくると、相手の保険会社から被害者に対して、治療費の支払いの打ち切りが通告されることがあります。
特に問題となるのがむち打ち症に代表される、自覚症状のみの怪我の場合です。
この治療費の打ち切りが妥当でなかった場合、治療の延長交渉を行い、治療費の支払いをしてもらった上で、治療期間に応じた慰謝料を支払ってもらう必要があります。
しかし、この交渉は容易ではない上、事故自体が軽微な場合、法律的にフォオーするのが難しいこともあります(裁判所も治療費の支払延長を認めないことがあります)。
このような場合、治療費の額がそれほど高額になっておらず、自賠責保険の保険金が十分に余っているような状態であれば、無理相手の保険会社と交渉を行うのではなく、自賠責保険金で治療費などを賄うということも選択肢の一つです。
なぜなら、自賠責保険の場合、簡易迅速に被害者を保護することを目的としているため、受傷自体が疑われるようなケースでなければ、厳格に治療費の支払いが打ち切られるということは基本的にないからです。
他にも、主婦の休業損害が絡む場合など、場合によっては自賠責保険金の方が裁判基準で計算するよりも高くなるということはあり得ます。このようなケースで敢えて低い裁判基準の額で示談をすべきではありません。
まとめ
上で見たように、多くのホームページで書かれているような「自賠責基準<任意保険基準<裁判基準」という図式が常に成立しているわけではなく、特に、「任意保険基準>自賠責基準」という部分については、そうではないことが多いので、この辺りをどう理解しているかは、本当に交通事故に強い弁護士なのかどうかが問われる部分だと思います。
保険会社から提示されている金額からどれだけの増額が見込めるのかについては、個々の事情によって異なりますので、実際に交通事故に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
・関連記事
「後遺障害の慰謝料」